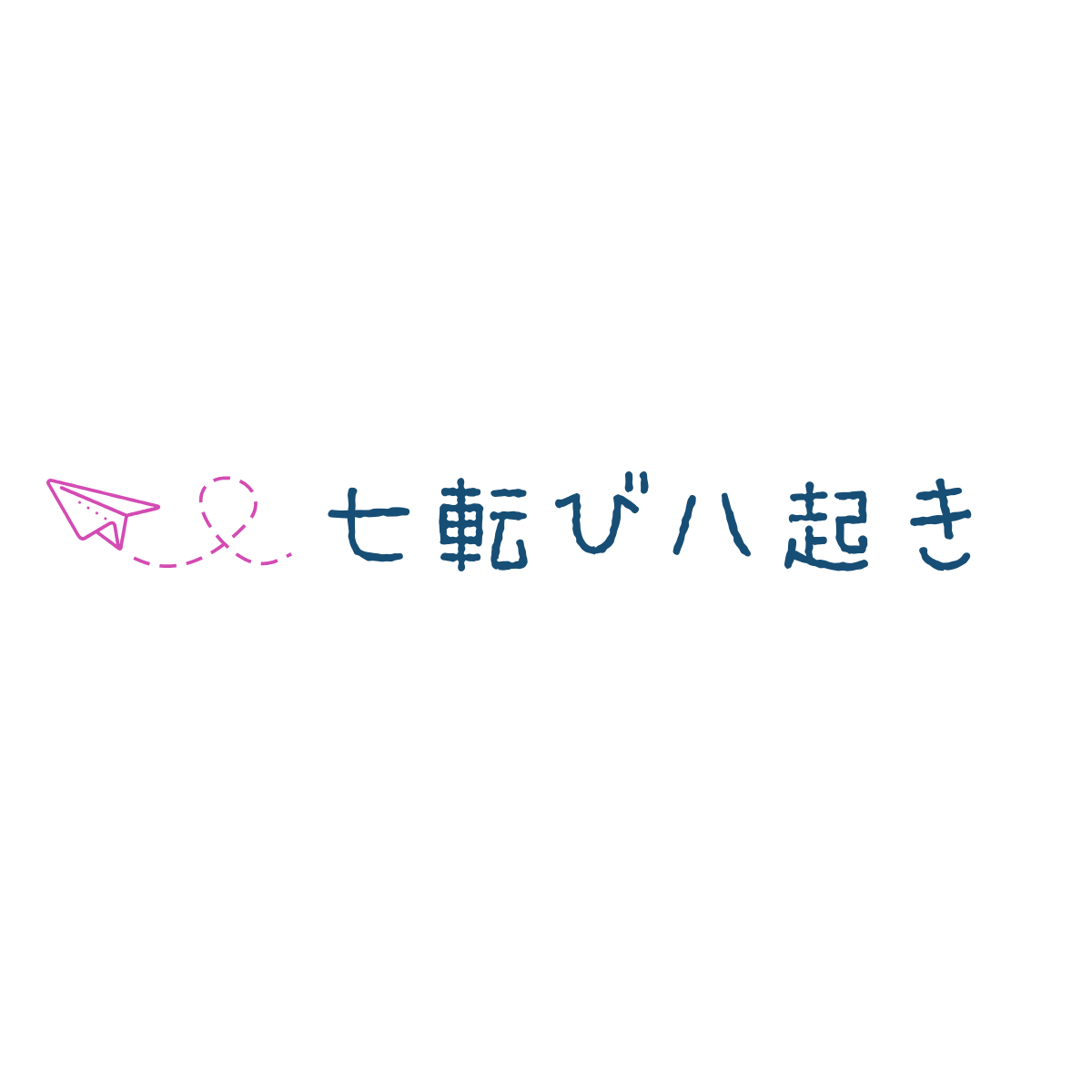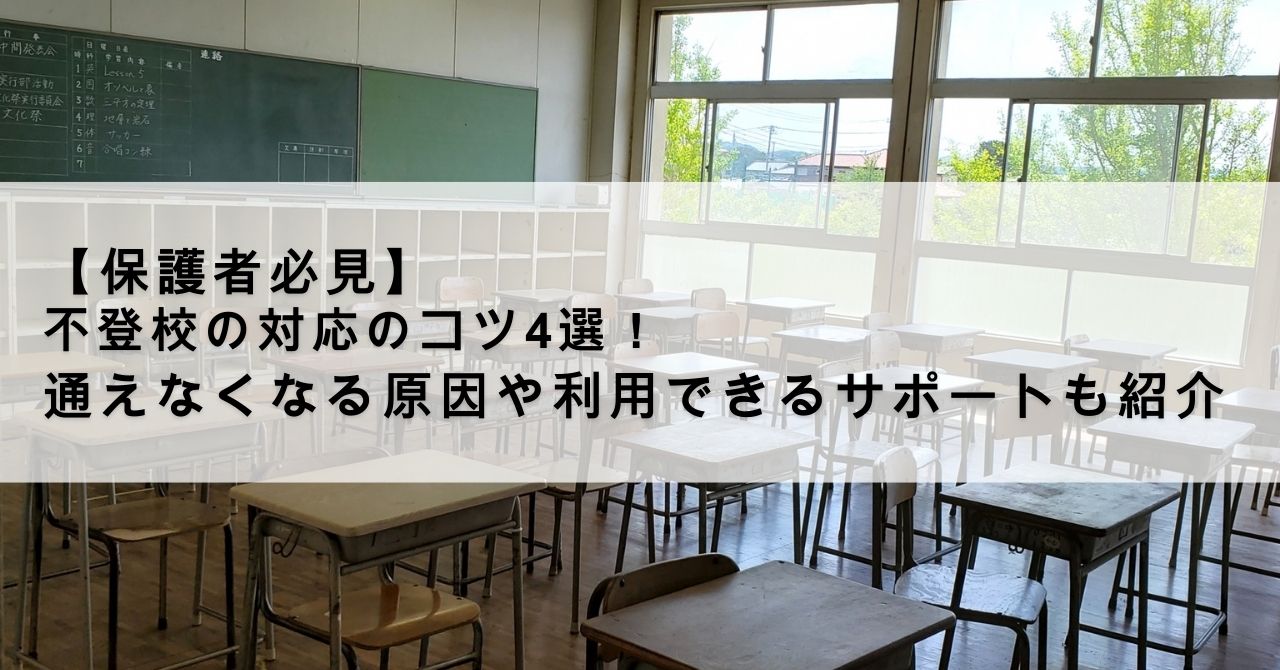老人ホームの費用が払えない!すぐできる対策から予防策まで徹底解説
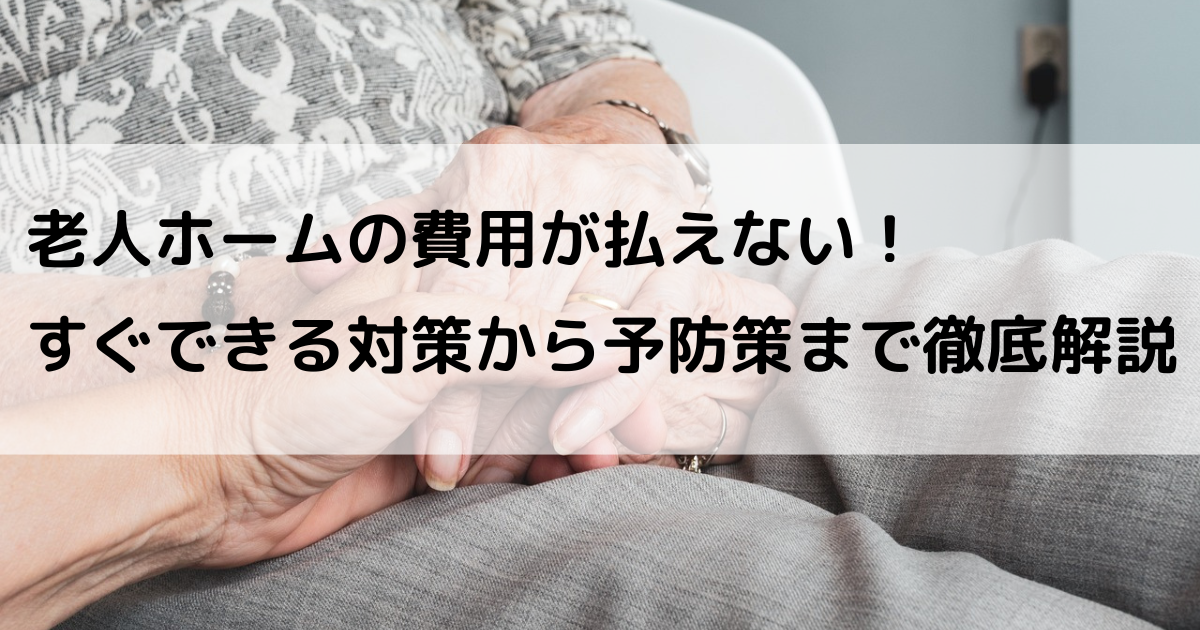
「父だけでなく母にも介護が必要になり、老人ホームの費用が払えなくなりそう」
「親の認知症が進んだようで、入所している施設の支払いができていないようだ」
「介護が必要になったけど、お金に余裕がない…」
この記事ではそんな悩みにお答えしていきます。
介護に追われる中でお金の問題が起きてしまうと、本当に嫌になってしまいますよね。
でも、そのままにしておくわけにもいきません。問題が大きくなってしまう前に、周囲の協力を得ながら解決していきましょう。
この記事では、以下の内容について解説します。
- 老人ホームの費用が払えなくなると起こること
- 老人ホームの費用が払えない状態になる3つの理由
- 老人ホームの費用が払えないときに施設に相談すること3つ
- 老人ホームの費用が払えない時に検討できる制度7つ
- 老人ホームの費用が払えない状況を防ぐためにできること3つ
私は精神保健福祉士・社会福祉士として10年以上、問題を抱える本人・家族の支援を行ってきました。
今、老人ホームの費用問題に直面して困っている方はもちろん、この先介護が必要になった時の費用が気になる方にも価値のある情報をお伝えします。

ぜひこの記事を参考に介護の費用に対する不安を減らし、介護する方もされる方も穏やかに過ごせる環境を作っていきましょう。
老人ホームの費用が払えなくなると起こること

老人ホームの支払いが遅れても、即日追い出されてしまうことはありません。とはいえ、滞納の状況が続くと強制退去もありえます。
まずは滞納になった時に起こることを押さえましょう。
- 連帯保証人に連絡がいく
- 支払いの猶予期間を過ぎると退去勧告も
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.連帯保証人に連絡がいく
支払いが遅れると、施設から連帯保証人に費用の請求がいきます。
施設は営利団体であり、発生した利用料を帳消しにはできません。本人が費用を払えなくなった時のために、入居の際に連帯保証人を求める施設がほとんどです。
支払いが滞っている場合は、施設から連絡が入る前に、本人または家族から連帯保証人へ状況を説明しておくのが望ましいでしょう。
2.支払いの猶予期間を過ぎると退去勧告も
支払いが遅れたらすぐに退去を求められるわけではなく、通常は数ヶ月の猶予期間が設けられています。具体的な期間は施設により異なるため、入所時の書類(重要事項説明書)を確認しましょう。
猶予期間を超えても滞納が続くと、退去勧告を受ける可能性もあります。そうなる前に、施設やケアマネジャーに相談することが重要です。
老人ホームの費用が払えない状態になる3つの理由

これまでの間は大丈夫だったとしても、何らかの問題が起きてしまい費用の支払いに困ることもあります。
どういう理由で老人ホームの費用が払えなくなってしまうのか、よくある3つの理由について解説します。
1.施設の利用料が上がったため
老人ホームの利用料は固定ではなく、むしろ料金は上がる可能性が高いということを知っておきましょう。同じ施設でも利用したサービス内容や介護度により利用料金は変わります。
たとえば以下のような要因で利用料が高くなるケースがあります。
- ヘルパーに入浴の介助をしてもらうなど、介護サービスの利用が増えた
- 要介護度があがった(施設の料金システムによる)
- 施設の利用量が底上げされた
施設の利用料が入所時からずっと変わらないという保証はありません。月々の請求書や引き落としの金額はこまめにチェックしましょう。
2.支払いに充てられる費用が減ったため
入所時は問題がなくても、さまざまな状況の変化により、費用の支払いが困難になるケースもあります。
たとえば、子どもの収入を頼りにしている場合、子どもが失業状態になることで、援助が途絶えてしまうことがあります。働き盛りであっても、予期せぬ病気や事故で働けなくなる人もいるのです。
また、本人の収入だけで支払いができていても油断は禁物です。配偶者が病気になり、介護のお金が必要になると、施設の費用が捻出できなくなる事態も考えられるからです。
施設入所後も、収入と支出の変化に注意を払い、定期的に見直す姿勢が大切です。
3.認知症などで本人のお金が引き出せなくなったため
支払いを本人がしている場合、本人が手続きできなくなり老人ホームの費用が滞納になるケースもあります。
たとえば認知症が進行してしまい本人が銀行からお金を引き出せなくなったり、急な怪我や病気で本人が入院してしまい手続きができなくなったり…。
たとえ家族でも、本人が意思表示をできない状況では本人のお金を引き出すことは難しいものです。
本人のお金が動かせなくなってしまったら、成年後見制度など利用できる制度を検討しつつ、手続きが完了するまでの間の支払いをどうするのか考える必要があります。
老人ホームの費用が払えないときに施設に相談すること3つ

今後のことは本人家族だけでなく、施設の責任者や相談員にも助言をもらいながら考えていきましょう。相談のポイントは以下の3つです。
1.猶予期間の確認をする
まずはいつまでに支払いを済ませなくてはいけないのか、具体的なリミットを確認しましょう。
- すでに滞納となっている分があるのか
- 払える目処はあるのか
- どのような理由で支払いが難しいのか
事情によっては施設の取り決めよりも長く待ってもらえる可能性もあります。支払いが難しい状況をありのままに施設へ説明し、判断を仰ぎましょう。
2.滞納分の返済計画を立てる
一時的に費用の支払いが難しいだけなら、きちんと返済計画を立てることで慣れた施設から退去せずにすむことも。滞納している金額を一括で支払えなくても、月々に分割して返済するなどの策を講じてもらえる場合もありますよ。
また、少しでも経済的負担を軽くするために、現在の施設の利用料を下げられないかも考えてみましょう。たとえば、洗濯物はリース(業者委託)ではなく家族で対応するなどの工夫が考えられます。

3.支払い困難な状況が続くのであれば退去や転居を検討
どんなに気に入った施設でも、費用が払えないのであれば利用継続はできません。新しい環境での生活資金を確保するためにも、費用の合わない施設からは早めの退去が望ましいです。
とはいえ、次の施設や生活場所が決まらないままに退去するわけにはいきません。
実家や子どもの家に身を寄せる選択肢もありますが、その場合、家族にかなりの負担がかかってしまうため、おすすめはできません。
事情をわかってくれている施設の職員やケアマネから、条件に合う施設や介護の方法について紹介やアドバイスをもらいましょう。
老人ホーム紹介サービスの利用や、自治体への相談も一手です。
老人ホームの費用が払えない時に検討できる制度7つ
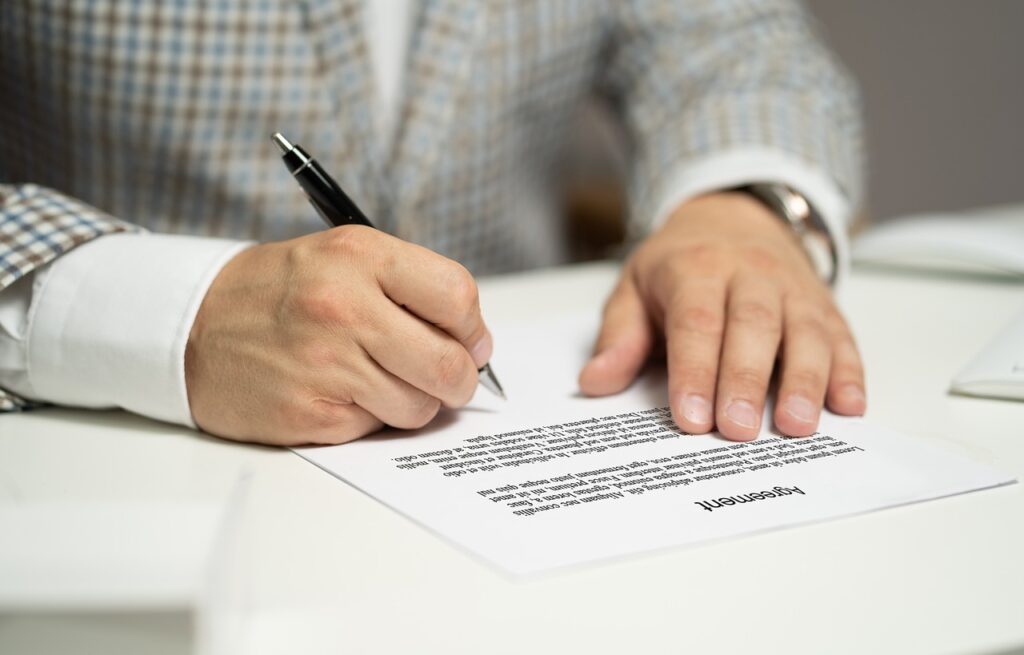
ここでは介護費用を軽減する制度について紹介します。介護費用を調達するための私的なサービスについても併せて案内します。それぞれの概要を表にまとめたので、参考にしてください。
| 制度/サービスの名称 | 概要 | 相談先 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 介護保険の自己負担額を軽減する | 自治体 (市役所介護保険課など) |
| 高額介護合算療養費 | 介護保険+医療保険の自己負担額を軽減する | 健康保険窓口 (市役所国保医療課など) |
| 特定入所者サービス費 | 介護保険施設(※)の食費・宿泊費を助成する | 自治体 (市役所介護保険課など) |
| 生活福祉資金 | 低所得者のために、無利子または低利子で生活資金を貸し出す | 社会福祉協議会 |
| 生活保護 | 国の定める基準より収入が低い人に保護費を支給する | 福祉事務所 |
| リバースモーゲージ | 持ち家を担保とした民間銀行のローン | 民間銀行 |
| マイホーム借り上げ制度 | 空き家をJTIが借り上げ、賃料を支払うサービス | 一般社団法人移住・住みかえ支援機構 (JTI) |
他にも自治体独自の助成制度を実施している場合があります。費用のことで困っているのであれば、早めにお住まいの自治体(市役所や地域包括支援センターなど)に相談しましょう。
老人ホームの費用が払えない状況を防ぐためにできること3つ

施設入所で困らないためには、日頃からの備えが大切です。すぐに取り入れられるポイントを3つ紹介しますので、ぜひ1つでも取り入れてみてください。
1.介護の専門家に相談できる体制を作っておく
いよいよ困ってからではなく、元気なうちから介護の専門家とのつながりを作っておきましょう。
たとえ相手が介護や施設探しのプロだとしても、初対面の人に資産状況など、踏み込んだ事情を伝えるのには抵抗があるのは当然です。「この人になら相談できる」と思える専門家が身近にいると、いざという時も安心です。
介護保険の利用はなく家族のサポートだけで生活ができているという人は、介護サービスに慣れる意味合いも含めて、ヘルパーやデイサービスなどを利用してみましょう。
サービス利用を始めると、必ずケアマネージャー(介護支援専門員;介護の相談ができる専門家)がつきますので、以後困ったことがあると相談にのってもらえます。
また、今は何でも一人でできる人でも、地域包括支援センターで開催されているお茶会や体操などの行事に積極的に参加してみてください。
地域包括支援センターは市町村ごとに設置されている地域の高齢者のための相談窓口です。どこにあるのか、どんな人がいるのか知っているだけでも相談がしやすくなります。
2.本人の意向や経済状況を把握しておく
本人がどのような生活を望んでいるのか、資産がどの程度あるのか、日頃から本人の思いや状況を把握できていますか?
急な病気や怪我で、至急老人ホーム探しが必要になるケースは多いです。
たとえば、

「病院から退院を迫られ、本人の経済状況が把握できないまま慌てて施設へ入所したら、びっくりするくらい本人にお金がなかった・・・」
などという話もあります。
また、費用に合う施設に入所できたとしても、本人が

「こんな施設は嫌!」
と強く抵抗され、転居せざるを得なくなるケースもあります。
せっかく入所した施設をすぐ退去することになると、精神的にも経済的にも辛いものです。そんな事態にならないように、できるだけ本人・家族間で思いや情報を共有しましょう。
本人にうまく聞き出せない、話を切り出せない場合はエンディングノートを活用するのもおすすめです。
さらに、成年後見制度の利用について、家族で話し合いができるとなお良いでしょう。成年後見制度とは、判断能力が低い方の財産や権利を守るための制度です。手続きをすると、法的に認められた代理人が本人の財産管理を行えるようになります。
3.介護=施設ではなく在宅介護という選択肢も
とくに介護に不慣れな家族は、経済的に無理をしてでも「安心だから」と施設入所を最善の策と思いがちです。
しかし、一概に施設入所が良いとは限りません。高齢者にとって、環境が変わることは大きなストレスになるからです。
「施設に入ったら何だか元気がなくなってしまった」「久しぶりに面会に行ったら、私が娘だとわかってもらえなかった」という声を聞いた経験がある人もいるでしょう。
また、施設入所を希望しない高齢者もいます。
令和2年に公表された厚生労働省の調査で「治る見込みがない病気になった場合、どこで最期を迎えたいか」という質問に対し、55%の人が「自宅」と回答しています。
介護は、施設だけでなく自宅でも行えます。
在宅介護のメリットとして、施設入所より費用を抑えられる点が挙げられます。令和3年の生命保険に関する全国実態調査では、介護費用は施設の場合月12万円、在宅では月4.8万円という結果でした。
在宅介護をする場合も家族が24時間見守る必要はありません。デイサービスやショートステイのような本人が外に出かけるサービスを利用すれば、家族の負担を減らせます。

ぜひこの記事を参考に、無理のない介護の方法を検討してみてください。