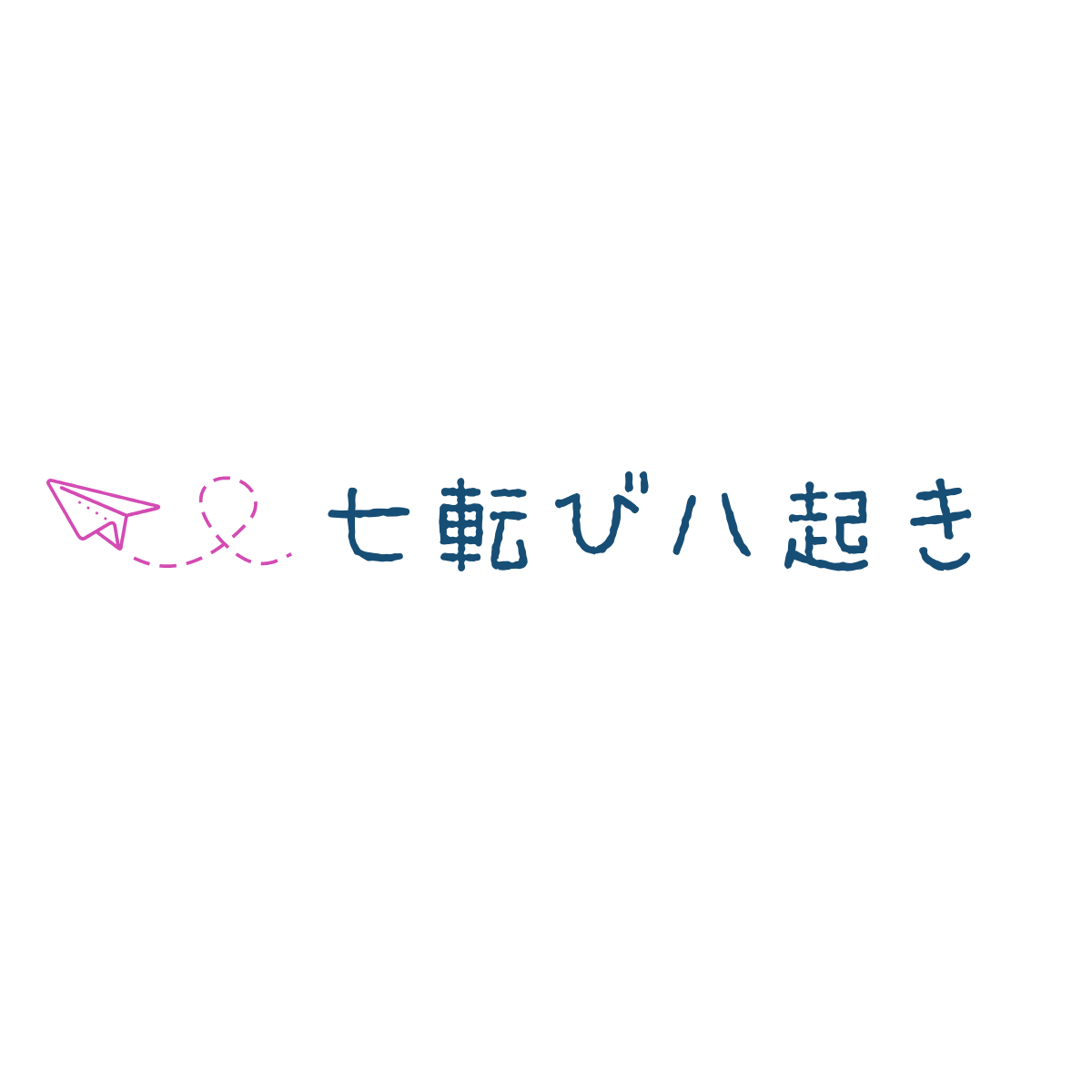【保護者必見】不登校の対応のコツ4選!通えなくなる原因や利用できるサポートも紹介
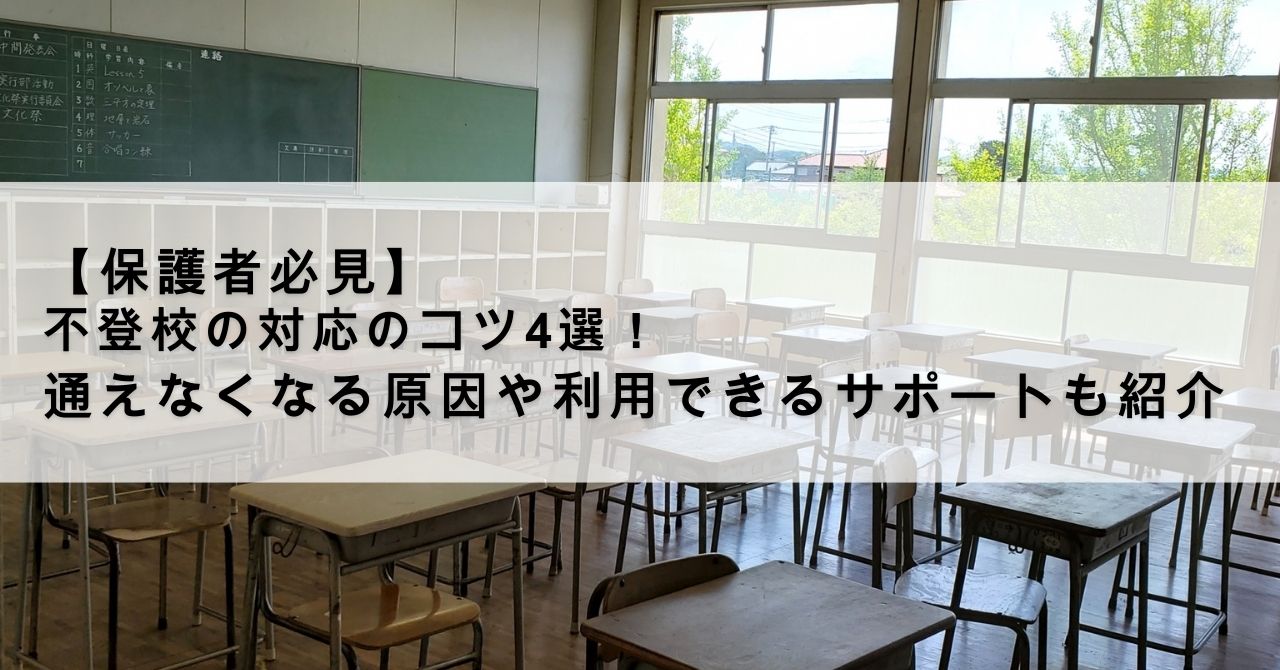
「嫌がる我が子を学校に行かせるべきか迷う」
「学校を休んでいる子どもにどう接したらよいのかわからない」
「不登校が続いており、学習の遅れが気になる」
我が子が不登校になると「まさかうちの子が…」と戸惑い、どうすべきか悩む方もおられるのではないでしょうか。
不登校の子どもは年々増えており、令和5年の文部科学省の調査では、過去最多の34万人を記録しました。これは年間30日以上欠席している子どもの数であり、行きしぶりや半日登校など、学校に行きづらさを感じている子どもの数はさらに多いと予測されます。
そこでこの記事では、不登校に悩む保護者の方に向けて、以下の内容について解説します。
- 学校に行けなくなるおもな理由
- 子どもと家で過ごす際の4つのポイント
- 不登校の相談先や教育サービス
体験談を交えながらわかりやすく解説します。不登校の不安を解消し、子どもの笑顔を取り戻すためにぜひ最後までお読みください。
出典:令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果概要|文部科学省
【体験談あり】不登校のおもな理由を5つ紹介

学校に行けない日が続くと、子どもに何があったのか心配になりますね。解決への糸口を探るために、不登校のおもな理由を5つ紹介します。
ただし、不登校にはさまざまな理由があり、原因はひとつとは限りません。さらに、子ども自身が言葉にできない問題を抱えている可能性もあることを知っておきましょう。
それぞれX(旧Twitter)の実例をもとに、文部科学省のデータを交えながら紹介します。子どもの状態を理解し、より良いサポートをするためのヒントとしてお役立てください。
出典:文部科学省委託事業 不登校の要因分析に関する調査研究 報告書|文部科学省
1.先生とのトラブル
先生とのトラブルは不登校の原因のひとつです。不登校の子どものうち、17%は教師とのトラブルや叱責を理由に挙げています。
もしも、小1の時に担任が忘れ物で毎日大声で怒鳴っていなかったら、もしも、担任がみんなの前でうちの子に「忘れ物するなんてダサいよ」って言っていなかったら、きっと今も行けていた。ただ、あんな環境に行かせたいとももう思えない。行く価値あるんか?としか‥。
— takachan (@WataridoriD) November 10, 2024
教師から理不尽に否定されたり、叱られたりすると当然傷つきます。また、教室内で目立つことで居心地の悪い思いをするでしょう。
教師とのトラブルは、学校にも対応を求めながら解決すべき問題です。
ただし、子どもの言うことを鵜呑みにするのは良くありません。とくに低学年の子どもは、説明する力が不足している場合があります。
子どもの気持ちに配慮しながらも、冷静な対応を心がけるようにしましょう。
2.友達とのトラブルやいじめ
友達とのトラブルやいじめも不登校の見逃せない要因です。
五年生娘の担任。とても評判も良く感じの良い先生。もしも、不登校の大きな要因となったお友達トラブル、イジメが無ければ学校に通えていて、高学年として学校ライフを楽しんでいたのかな…なんて思ってしまった。この先生なら楽しいクラスになりそう。
— Sakura (@Sakura53886464) April 20, 2024
学校では集団行動が基本です。クラスに馴染めない場合は孤独感を感じてしまい、学校に行くのが嫌になるケースもあります。また、いじめの問題は増え続けており、他人事ではありません。
いじめは、被害者に非はなく、許されない行為です。しかし、いじめを受けた本人は恥ずかしさから周囲に助けを求められないことも。トラブルがないか、周囲の大人が注意を払う必要があります。
3.体調不良
厚生労働省の調査によると、不登校の子どものうち69%は頭痛や腹痛、吐き気、などの体調不良を感じています。
行きたいのに行けない。
— めめ (@meme_HD14) November 19, 2024
久しぶりに息子の涙を見た。
行きたかった、行けると思ってた
なのに頭痛が出る。
自分でも分からなくて悔しくて
泣いてる。
私が少し責める言い方を
してしまったから。
中学生男子の涙は辛い。
これが不登校。
行きたいのに行けない。
1番辛いのは本人。
学校に行く直前になると体調不良を訴えるため、親はつい仮病を疑ってしまうかもしれません。しかし、身体の病気がなくても、学校へ行く不安やストレスが身体的な症状となって出現することもあります。体調不良が続く場合は、小児科や心療内科の診察を検討するのも良いでしょう。
4.学業の不振
不登校になったきっかけとして、47%の子どもが学業の不振と回答しています。授業についていけない状況は、不登校につながります。
「こんな知能でやってられっかよ!」ってのが俺が不登校になる理由だし、イライラとか落ち込みの原因なんだと思う。精神科に行ってそれがハッキリ数字で出て、ある意味スッキリしたんだが解決策はない。多動が多少コンサータで良くなり、肩こりがパキシルで良くなった。しかし知能に効く薬はない。
— えりぞ (@erizomu) November 14, 2024
もしも自分のレベルにあった公立高校に進学してたら、かな?
— amw (@amw_amw699) November 9, 2024
ハイレベルの私立高校に行って、勉強ついていけないし、塾に行かせるにも学費で無理だったからな。
落ちこぼれて不登校に。
勉強に向き合うのが辛くなると、朝から夕方まで授業を受ける必要のある学校が嫌になるのはイメージできるかと思います。なかには発達の特性が隠れているケースもあり、本人に努力を求めるだけでは改善が難しいことも。
また、平均以上の学力がある子どもの場合も、周囲からの過度な期待がプレッシャーとなり、不登校につながることもあります。
5.なんとなく(特に理由はないが学校には行けない)
意外かも知れませんが、不登校になった原因を自分で説明できる子どもは少ないものです。
長女が学校に行きたくないと泣きながら言ってきた。理由を聞くと特になにもないけど学校に行こうと思うと具合が悪くなる。って。どうしたらいいのだろうか…。
— あみ\♡︎/不安障害治療中 (@__ami0602) November 25, 2024
いじめられてるわけでもない。学校に行けば仲のいい友達がいる。学校に行った日は放課後遊びにも行く。なんでだろう…
不登校は、さまざまな要因が重なり合って起こる複雑な問題です。加えて、子どもは成長段階にあります。自分が不登校になった原因がわからなくても不思議ではありません。
子どものはっきりしない様子を、周囲はじれったく感じるでしょう。一方で、理由が明確にならなくても、不登校を改善することは可能です。理由を探すより、本人の成長や環境の変化が大切であることを知っておきましょう。
我が子が不登校になった際の4つの対応法

不登校の子どもに接する際は、以下の4つの点に注意しましょう。
もちろん、全てを完璧にこなす必要はありません。しかし、これらのポイントを意識するだけでも子どもへの対応が変わり、不登校の解決につながるでしょう。
不登校の解決に時間がかかる場合もありますが、笑顔で過ごせることを第一に、子どもと向き合っていきましょう。
1.学校に行くことを強要しない
親が学校に行けそうだと思っても、子どもにその気がないのであれば、できるだけ休ませてあげましょう。無理をして登校すると、かえって不登校が長引く可能性があるからです。
子どもが家で普通に過ごしている姿を見ると、つい学校に行かないのは甘えではと思ってしまう日もあるでしょう。しかし、不登校が続くのには何らかの理由があるのです。
仕事や介護など、親の都合もありますが、できるだけ子どもを優先してあげてください。問題が解決すれば、子どもは学校に行けるようになります。
2.子どもを責めない
「明日は学校に行く」と子どもが言っても、いざ当日になると休んでしまう場合もあります。親には親の都合があるため、つい「昨日約束したのに」「他の子は普通に行っているのに」と子どもを責めたくなることも。
しかし、誰よりも子ども自身が学校に行けない自分を責めています。子どもも、皆と同じように普通に学校に行きたいと思っているのです。
子どもを批難したところで、学校に行けるようにはなりません。責任を追求するのではなく、状況を良くするための方法を考えていきましょう。
3.ありのままの子どもを認めてあげる
不登校の子どもの多くは、学校に行けない自分を責め、自己肯定感(そのままの自分を認めてあげる力)が低くなっています。自己肯定感が低い子どもは、「どうせ自分なんて」といろいろなことに挑戦する気持ちが持てず、不登校がなかなか改善しない傾向があります。
早く不登校を解決しようと焦ると、子どもに対し、つい小言が増えてしまいます。そうなると子どもが家のなかでリラックスして過ごせず、自己肯定感も高まりません。
当然ですが、子どもはかけがえのない存在で、1人ひとりに良いところがあります。一緒に趣味を楽しんだり、小さな行動でも褒めてあげたりと、自信をなくし不安になっている子どもを安心させてあげましょう。
4.生活リズムを整える
学校を休んでいる間も、夜更かしをせず、規則正しい生活を送れるように気をつけてあげましょう。とくに、睡眠を十分にとることは重要です。睡眠不足が続くと自律神経が乱れ、気持ちが不安定になったり、頭痛が起きたりします。また、朝起きられないと登校時刻に間に合わないため、余計に登校へのハードルが上がってしまいます。
スマホやゲームのしすぎは睡眠不足につながるため、注意が必要です。ただし、子どもがひどく疲れているのであれば、規則正しい生活を送るよりも自分の好きなペースで過ごす方が良い場合もあります。学校を休んでいる間の過ごし方に不安がある場合は、専門家へ相談しましょう。
家庭で抱え込まず、周囲にサポートを求めよう

子どもが不登校になった場合は、家庭の努力だけで解決しようとせず、早めに周囲のサポートを求めましょう。不登校にはさまざまな問題が絡んでおり、家庭内の努力だけでは解決できない場合もあります。学校やカウンセラーの協力が得られると、スムーズな問題解決が望めます。
また、第三者への相談は、保護者の不安を解消するためにも大切です。相談先があれば親の不安に寄り添いながら、必要な情報を教えてもらえます。
友人に相談するのも一手ですが、親の会など、同じ境遇にある人とのつながりを作ってみるのもおすすめです。当事者ならではの共感や、有益な情報を得られるでしょう。
不登校は家庭や子どもだけの問題ではありません。周囲の目を気にして悩むより、積極的に周囲へ相談するようにしましょう。
不登校のサポート先を相談する順に紹介

学校は、勉強のほかにも、集団行動を通じて社会性を身につける場でもあります。学校に行けない日が続くと、子どもが学力や社会性を身につけられるか、心配になるときもあるでしょう。
不登校の子どもへの一般的な対応としては、まずは今通っている学校へ戻ることを目標とします。諸事情により、それが難しい場合には、子どもの成長をサポートするために、学校以外の居場所を検討する必要も出てきます。
相談の順番としては、次のような流れをイメージすると良いでしょう。
順番に解説します。
1.通っている学校
不登校の相談先としてまず挙げられるのは、担任の先生です。学校で、最も子どもと関わる機会が多く、家庭ではわからない学校での様子や、クラスでのトラブルについても把握しているからです。
不登校は、子どものせいではなく、学校の体制の問題であるという考え方が広まってきています。学校の先生は、子どもが学校に行けるように、オンライン授業や別室登校など、本人に合う方法を検討してくれるでしょう。
もし担任の先生に相談がしづらい場合には、校長や教頭に相談しても良いでしょう。さらに、学校には勉強を教える教師以外にも以下のようなスタッフがおり、不登校の相談が可能です。
| 養護教諭(保健室の先生) | 子どもが安心して過ごせる場所(保健室)を提供し、こどもを休ませてくれたり、話を聞いてくれたりする |
| スクールカウンセラー | カウンセリングを通じて子どもの心のケアを行う |
| スクールソーシャルワーカー | 学校以外の機関とも連携しながら、子どもや家庭が抱える問題の解決をサポートする |
それぞれ連携を取りながら、不登校の子どもや家庭をサポートしてくれます。決まった日にしか学校にいないスタッフもいるため、相談の際は事前に予約をしておくのがベストです。
2.教育支援センター(適応指導教室)
通常クラスへの復帰までに時間がかかりそうな場合は、教育支援センターに相談してみましょう。教育支援センターは、再登校に向けた支援を無料で行う公的な機関です。親からの相談に対応するほか、子どもに対しカウンセリングや学習の機会も提供しています。
教員免許を持つスタッフが多く、一人ひとりのペースに合わせて指導してくれるので、学校の授業のペースについていくのが難しい場合も通いやすいでしょう。
3.学びの多様化学校やフリースクールなど
在籍している学校へ戻るのが難しい場合には、子どもの成長のために、学校に代わる新たな学びの場や社会との交流の場を持つ必要が出てきます。具体的には、以下のような選択肢が考えられます。
| 名称 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| 学びの多様化学校(特別不登校特例校) | 小学生・中学生・高校生 | ・不登校の子どもに向けた、特別なカリキュラムを提供する学校 ・全国で35校(令和6年)と数が少なく、利用できる人は限られる |
| フリースクール | 小学生~高校生 (施設により異なる) | ・学びや体験活動などを提供する民間団体 ・カリキュラムや費用が施設によって大きく異なる |
| 家庭教師 | 小学生~高校生 | ・学びや体験活動などを提供する民間団体 ・カリキュラムや費用が施設によって大きく異なる |
もちろん、不登校になってすぐに結論を出す必要はありません。ただ、多くの選択肢があると知っておきましょう。
不登校は焦らずに周囲の協力を得ながら対応しよう

不登校になると、子どもが将来、社会に適応できるのか心配になる人もいるでしょう。しかし、悲観する必要はありません。
不登校を経験した人のうち、8割は20歳の時点で就職や就業をしています。不登校になっても、将来的には自分の力で社会に出ていけるのです。
また、現代社会ではさまざまな価値観を認める風潮があるなか、学校の在り方も変わってきています。文部科学省は2023年に、「誰1人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)を打ち出しました。どんな子どもでも安心して通えるよう、学校も変わろうとしており、不登校の子どもへのサポートに積極的です。
子どもの成長は家庭だけでなく、社会全体で支えるものです。周囲の協力を得ながら、焦らずに子どもの成長を見守っていきましょう。
出典:一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について|文部科学省
出典:「不登校に関する実態調査」 ~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(概要版)|文部科学省